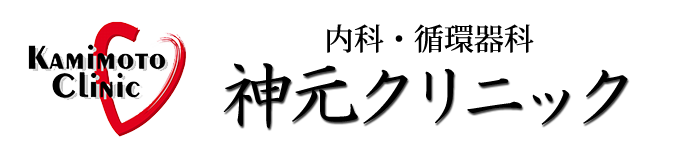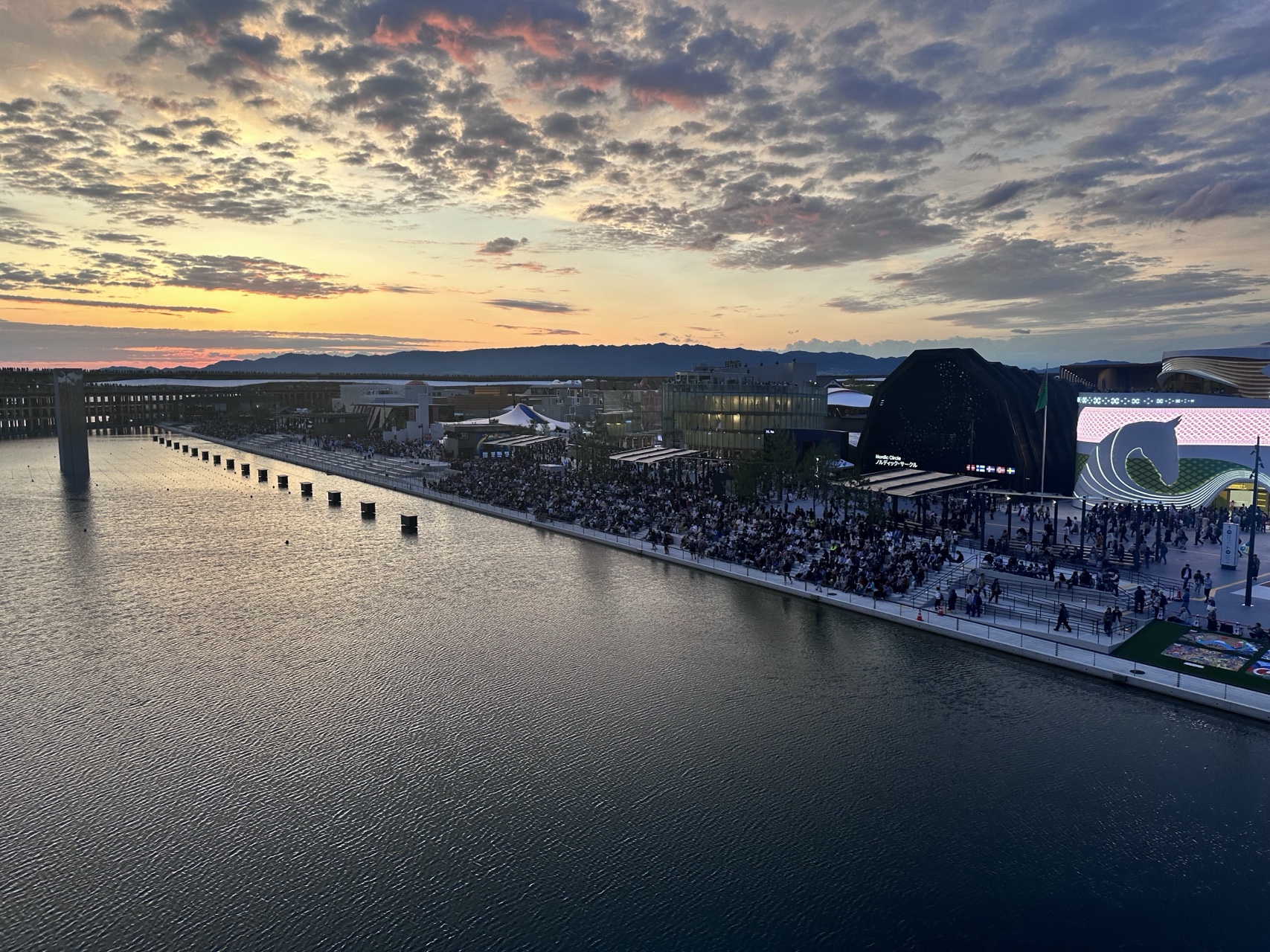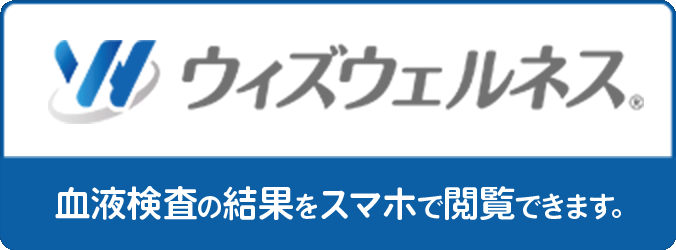75歳以上の高齢者の高血圧は血圧変動性が大きい、収縮期高血圧が多い、起立性や食後低血圧が多いなどの特徴があり、一概に年齢だけでは身体の活動性なども決められないこともあり
75歳以上の高齢者の高血圧については以下の4種のカテゴリに分類して降圧目標を立てることが推奨されています
①カテゴリー1:自力で外来通院が可能な方で目標は130/80以下です
②カテゴリー2:外来通院に介助が必要な方で140/以下を目標とするが合併症のある場合には130/以下を目標とする
③カテゴリー3:外来通院が困難な方で150/以下を目標にし120/以下にはしない
④カテゴリー4:エンド・オブ・ライフの方では個別に判断するが目標は140~160/で新たな降圧は開始しない
高齢者では降圧薬の副作用も出やすいので慎重に経過を見る必要があります