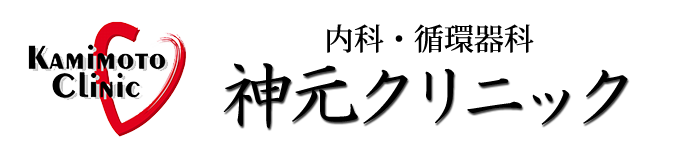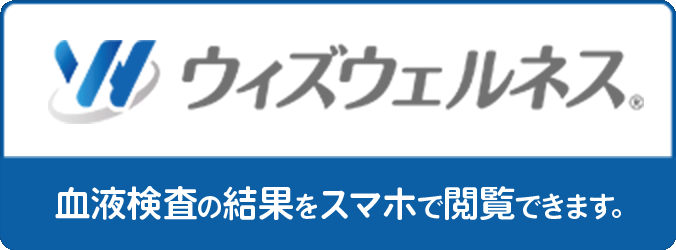今年もクリニックのつつじがきれいに咲きました
工事の影響で昨年までの半分の量なのですがとても鮮やかな色でまた一年が経ったなあと実感します
歴史小説を読むのが好きで、中井貴一主演の大河ドラマ「武田信玄」を観て以来多くの武田信玄に関する歴史書を読みました
江戸時代に編纂された「甲陽軍鑑」は歴史資料ではなく一般向けの娯楽作品の意味合いが強かったようです
江戸時代は徳川一強の時代ですが、その徳川が大いに苦しめられた武田信玄やその家臣は別格的な存在として庶民に語り継がれていたそうです
特に有名なのが三方ヶ原の戦いで、わずか数時間の戦闘で1万人近い徳川勢が壊滅し浜松城に逃げかえったときは100人に満たなかったと言いますからいかに武田信玄の軍事力が強大であったかが知れます
その直後に武田信玄は肺結核で命を落とし時代は大きく動きますから、彼のような偉人も病気には勝てなかったということですね
「人は石垣、人は城。人は城なり、城は人なり」は武田信玄の有名な言葉ですが、終生彼は人の心をつかむのに腐心したそうです
生涯城を持たず、つつじが崎と呼ばれる屋敷に住んだ彼はこのきれいなつつじを観ながら何を考えたのでしょうね?