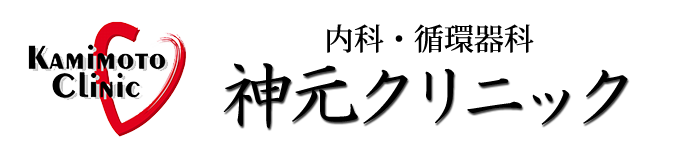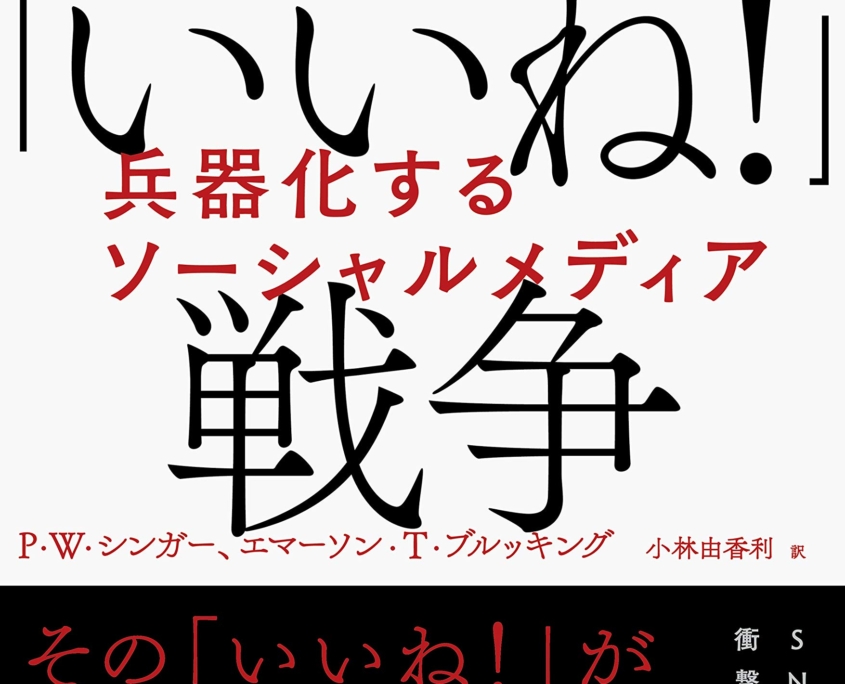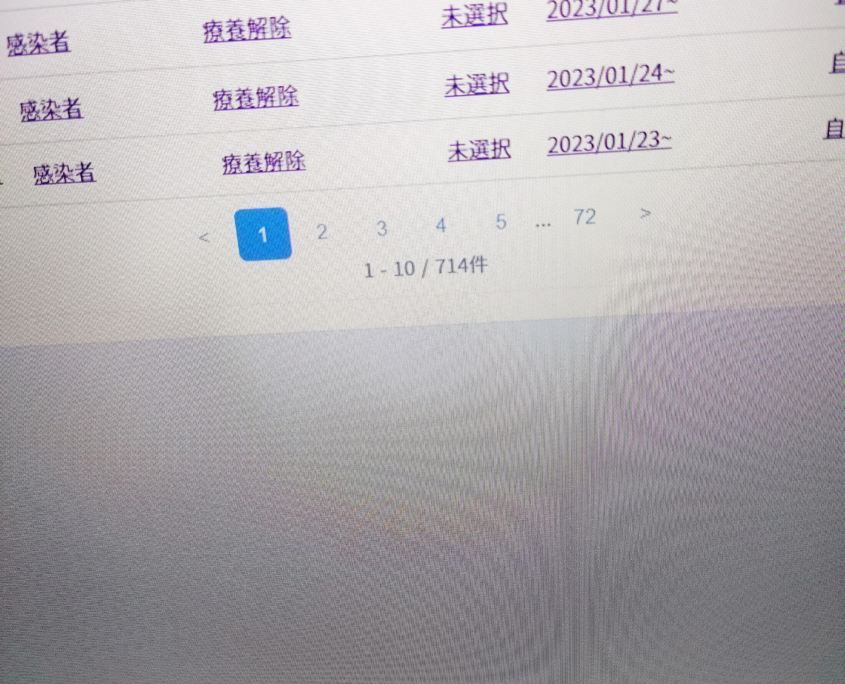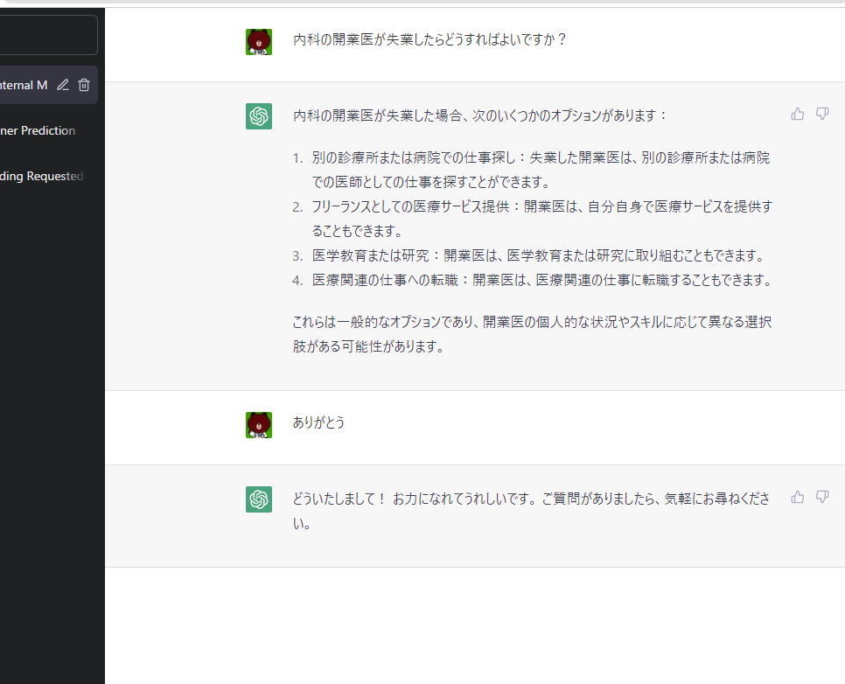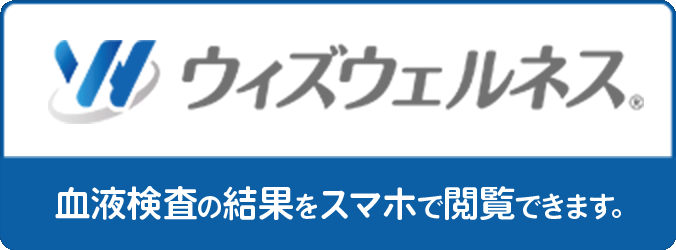左心室の機能を測る上で大切なのが拡張機能です。
収縮機能は左心室がポンプとしてどの程度血液を駆出する力があるかを測る、いわばポンプとしての能力です。
一方、拡張機能は左心房から左心室への血液の流入のしやすさです。
左心室への血液の流入は
・拡張早期
・心房収縮期
の二相に分かれます。
収縮を終えたばかりの左心室が自然に拡張する時点で左心房ー左心室間の僧帽弁が開き血液が流入します(拡張早期)。
そして、左心房から左心室への血液の流入が終わったころに、左心房が収縮しさらに左心室に血液を押し込みます(心房収縮期)。
一般には流量は
拡張早期>心房収縮期
ですが、左心室が硬くなり広がりにくくなると
拡張早期<心房収縮期
となります。
これは超音波検査で簡単に調べることができます。
この左心室の拡張機能障害は、高血圧や心筋症あるいは大動脈弁狭窄症のために左心室の筋肉が肥厚した状況などでみられます。
収縮機能の維持された心不全(HFpEF:ヘフペフ)はこういう状態で、分かりやすく言うと左心室に血液が流入しにくくなってその手前の肺に血液が渋滞を起こしている(肺うっ血)ことです。
「拡張機能障害による肺うっ血」と呼べば分かりやすいと思うのですが、なぜが学会では「収縮機能の正常な心不全」と呼ばれます。