RAS系阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬・アルドステロン受容体拮抗薬)と利尿剤は推奨される降圧剤の組み合わせで実際にアルドステロン受容体拮抗薬と利尿剤の合剤も発売されています
しかしながら個々のNSAID(非ステロイド系抗炎症薬)が加わるとtriple whammy(三段攻撃)と呼ばれる危険な併用になります
急性腎障害や腎機能低下のリスクになりうります
高齢高血圧患者や心不全、腎機能の低下した患者では特に注意が必要です

RAS系阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬・アルドステロン受容体拮抗薬)と利尿剤は推奨される降圧剤の組み合わせで実際にアルドステロン受容体拮抗薬と利尿剤の合剤も発売されています
しかしながら個々のNSAID(非ステロイド系抗炎症薬)が加わるとtriple whammy(三段攻撃)と呼ばれる危険な併用になります
急性腎障害や腎機能低下のリスクになりうります
高齢高血圧患者や心不全、腎機能の低下した患者では特に注意が必要です

 心室の内圧をP、
心室の内圧をP、
心室の内腔の半径をR、
心室壁にかかる張力をT とすると
T=2PR
という式が成り立ちます
たとえば高血圧などで左心室の内圧が上がるとそれだけ左心室壁にかかる張力は増加しますので増えた張力に対応するため左心室壁は内腔側に心筋を増生し内腔を狭くする心筋肥大(求心性肥大)がおこります
あるいはシャント疾患や弁膜症などで左心室に容量負荷がかかり左心室が広がるとその結果として心室壁にかかる張力が増えますのでその張力に耐えるために心室壁は肥厚し強度を増します
すなはち、拡大は必ず肥大を伴いますが、肥大は必ずしも拡大を伴いません
もし肥大を伴わない拡大があればそれは心筋そのものに異常があると言えます
拡張型心筋症はその例で、左心室の筋肉に異常がおこり収縮力が低下すると拍出量を保つために心室は拡大しますが、拡大したにもかかわらず肥大しません
超音波検査で拡大しているにも関わらず肥大のない左心室を見た場合、その時点で心筋の異常であると結論できます
心筋が収縮力を失う病気の中で頻度が多いのが拡張型心筋症です
現実には拡張型心筋症の原因は不明ですし、心筋症そのものを治す治療も現在のところありませんので心筋生検といったリスクのある検査はしないのが一般的です
拡張型心筋症に類似しした疾患には虚血性心疾患によるもの、心筋炎の後遺症、アミロイドーシスやサルコイドーシスがありますが、アミロイドーシスを除いて特異的な治療法はありませんし心アミロイドーシスの治療も一般に普及している段階ではないので治療は心不全対策になります
この分野は遺伝子レベルの研究が望まれる分野だと思います
75歳以上の高齢者の高血圧は血圧変動性が大きい、収縮期高血圧が多い、起立性や食後低血圧が多いなどの特徴があり、一概に年齢だけでは身体の活動性なども決められないこともあり
75歳以上の高齢者の高血圧については以下の4種のカテゴリに分類して降圧目標を立てることが推奨されています
①カテゴリー1:自力で外来通院が可能な方で目標は130/80以下です
②カテゴリー2:外来通院に介助が必要な方で140/以下を目標とするが合併症のある場合には130/以下を目標とする
③カテゴリー3:外来通院が困難な方で150/以下を目標にし120/以下にはしない
④カテゴリー4:エンド・オブ・ライフの方では個別に判断するが目標は140~160/で新たな降圧は開始しない
高齢者では降圧薬の副作用も出やすいので慎重に経過を見る必要があります

フラミンガム研究などの観察研究で収縮期血圧120以上から心血管合併症が増えてくることは以前から明らかにされており,収縮期血圧120は至適血圧値とよばれていました。
しかし降圧薬治療でこのレベルまで介入することの是非については多くの議論がありましたが、血圧を120以下に下げることの有用性を証明した大機御臨床研究がSPRINT試験です
収縮期血圧を120以下に降圧した場合には140を目標にした場合に比べて心不全や心筋梗塞などの心血管イベントが25%も低下し、全死亡も27%も低下したという結果を踏まえてアメリカでは高血圧の基準が130/80に引き下げられました
日本での高血圧の基準はそれには追随しなかったものの、2025改定の「高血圧管理・治療ガイドライン」では「120/80以上の血圧を呈するすべての者を血圧管理の対象とする」と宣言されています
ただちに降圧剤を内服するかは別にして生活習慣の改善などを開始することを推奨されています
ちなみにSPRINTでは血圧は医師のいない場所で自動血圧計で3回計測した血圧の平均値を血圧として採用しています
診察室での血圧は家庭血圧より高値である場合が多く血圧は家庭で測定することが基本だと思います

特に左の腎臓は130mmHgもの圧力がかかり太さ2センチ以上もある大動脈から数センチしか離れていないにも関わらず極めて細い血管にまで分岐し糸球体を形成します
ですので腎臓の中の微小な血管は太さに比べてすごく大きな圧力がかかっておりこれをストレインベッセルと呼びます
構造上血管壁のダメージを受けやすく血流の障害は蛋白尿のない腎機能低下につながります
こういう場合には降圧薬としてアルドステロン受容体拮抗薬の優位性はなく、カルシウム拮抗薬も選択肢になります
こういう状況は腎硬化症と呼ばれますが、全身の他の動脈例えば脳や心臓あるいは眼の血管でも同様のことがおこっている可能性がありますので注意が必要です

HFpEFの長期予後を改善する効果を証明された薬は長らくなかったのですが、2021年以降の臨床研究から糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬がHFpEFの標準的な治療薬として位置づけられました
しかしながらそれ以外の薬剤は未だに有効性が不明または無効でHFpEFの治療はまだまだこれからの分野です
また今年改定された高血圧のガイドラインでは、HFpEFに対して血圧を130未満にすることが推奨されています
その解説を見ますと
「HFpEFにおける収縮期血圧130未満の血圧管理は、130以上の管理と比して全死因死亡を26%減少させ統計的には優位ではなかったものの抑制傾向が認められた」
と若干歯切れの悪い表現です
個人的意見ですが、これはHFpEFというのが一つの疾患ではなく多くの病態をひっくるめて論じているからではないかと思います
左室収縮能の保たれた心不全、言い換えれば心臓の動きが良いにもかかわらず心不全であるというのはいろんなケースを含みます
最も多く想定されているのが
・左室拡張障害;左心室の収縮は良いが左心室が硬く広がりにくくなっているためにその手前の肺にうっ血がおこっている
だと思うのですが、それ以外に
・頻脈など不整脈によるもの
・弁の機能異常
・脱水
・腎機能低下などによる循環血液量の増加
などたくさんあると思います
ですからHFpEFはまずどのようなメカニズムでおこっているのかをはっきりさせ個々の血行動態に合わせた治療をするのが現状ではベストだと思っています
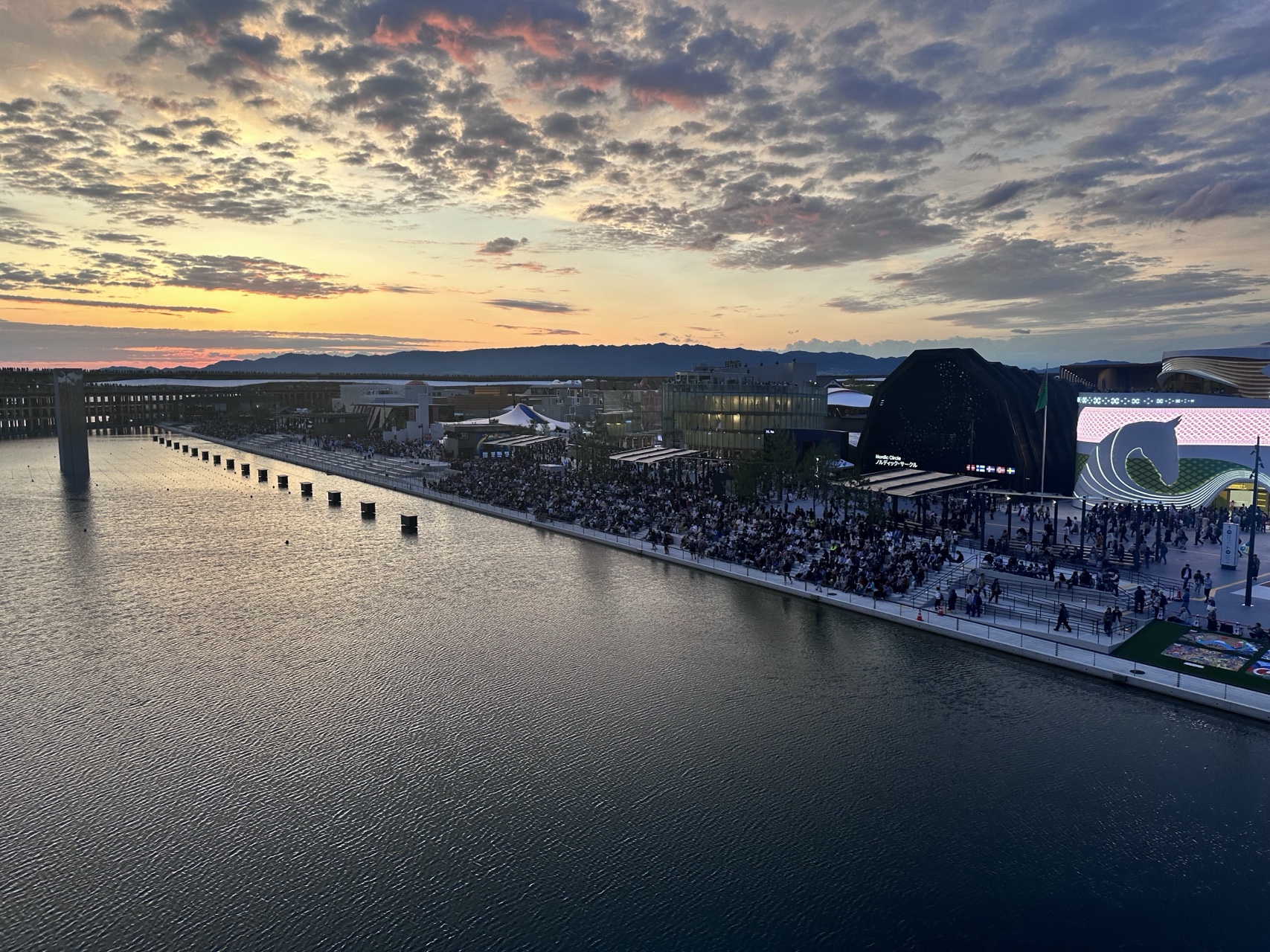
太平洋戦争を指揮したアメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領は重症高血圧だったそうです
死去したのが1945年の終戦直前でしたが、当時の血圧は300/だったと記録があります
脳出血でなくなったのですが、どうしてそんな血圧を放置したのでしょう?
理由は二つあります
・当時血圧は高い方が臓器血流が良くなる、すなはち血圧が上昇するのは良い反応だと信じられていた
・有効な降圧剤がなかった
意外なことですが高血圧治療の必要性が認識され、臨床に降圧剤が用いられるようになったのは戦後です
案外歴史の浅い治療なんですね
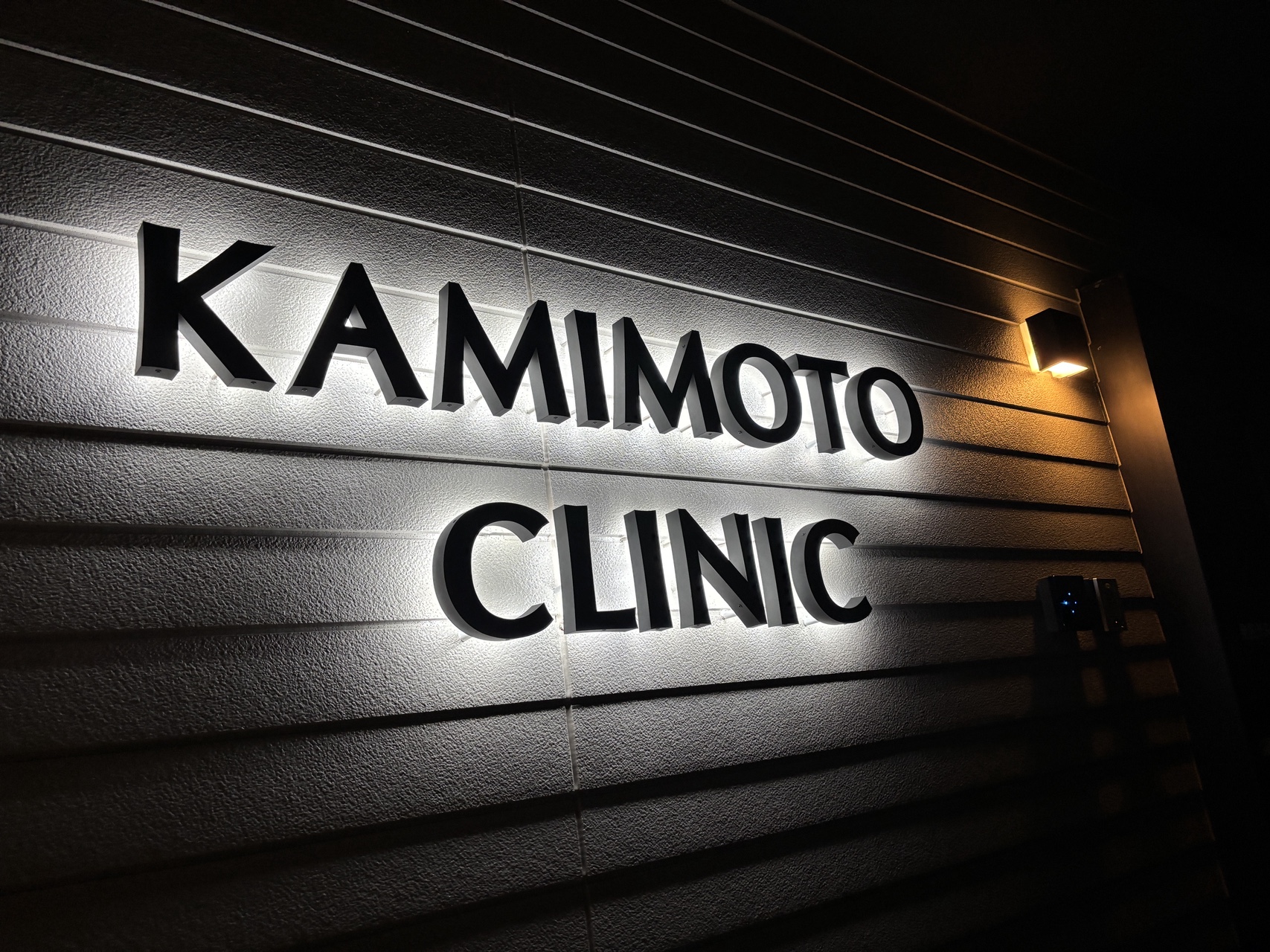
日本高血圧学会発行のガイドラインが今年改定されました
以前のものは
「高血圧治療ガイドライン2019」で今回改定されたのは
「高血圧管理・治療ガイドライン2025」
に名前自体が変わりました
そして第1部「国民の血圧管理」では高血圧の予防・啓発活動に従事する方々が利用対象となっており予防医学に重点が置かれています
ですので医師以外の方が読むことを想定されておりネット通販などで購入可能です
ご興味のある方は是非一度ご覧ください

慢性腎臓病とは
・糸球体濾過率60以下
・持続する蛋白尿
のいずれかに該当する場合を指します
実は慢性腎臓病という病名は比較的新しく私が研修医の頃はこういう呼び方はしませんでした
腎硬化症、IgA腎症、膜性腎症、巣状糸球体硬化症、膜性増殖性糸球体腎炎や糖尿病性腎症などと主に糸球体の病理診断を元に診断され目標は透析回避でした
しかしその後、こういった糸球体疾患の方々の命を脅かすのは末期腎不全よりむしろ脳卒中や心臓疾患などの方がずっと多いということが統計的に証明され、治療目標は透析回避よりむしろ心血管疾患予防にシフトしました
腎機能低下は一旦始まると自動的にどんどん低下するという性質があります
BrennerのHyper filtration theory (糸球体過剰ろ過仮説)はこの性質をうまく説明しています
腎臓で血液をろ過し尿を作る糸球体は片方の腎臓で約100万個ありますが、腎機能低下とはこの100万個全ての糸球体の機能が少しずつ低下するのではなく機能を失った糸球体がところどころに出現し正常な糸球体の数が減少する状態です
残された糸球体一つ一つには過負荷がかかり、ろ過を多くするために糸球体の出口の動脈を収縮させてろ過する圧を上昇させ全体としてなんとか機能を保ちます
つまり残された正常な糸球体にかなりの負担をかけている状態です
この状況ではさらにいくつかの糸球体が過負荷により機能を失い、正常な糸球体がさらに減っていくという説です
ですので腎機能は低下すればその低下自体がさらなる低下の原因になります
このため糸球体の濾過圧を低下させる降圧剤、主にアンジオテンシン受容体拮抗薬が治療薬として用いられます
本年改定された新しい高血圧治療ガイドラインでは降圧目標が一律に130/80(家庭血圧125/75)未満とされていますが、その目標を達するために選択するべき薬剤はやはりアンジオテンシン受容体拮抗薬です
ただし慢性腎臓病のうちでも有効性が証明されているのは蛋白尿が陽性のもののみです
これは糸球体硬化以外の腎硬化症などが存在し、そういった場合にはむしろ逆効果になる場合があるからです
糖尿病性腎症にはアンジオテンシン受容体拮抗薬が最適とされていますがこれもやはり蛋白尿がある、すなはち糸球体疾患である場合のみです
降圧剤は適応を誤ると、一見血圧は低下していても臓器保護という観点では逆効果になる場合があります

飲酒後に血圧を測定すると拡張期・収縮期ともに低下したという経験をお持ちの方は多いと思います
単回飲酒は数時間の間血圧を硬化させますが、長期間常用するとむしろ上昇します
高血圧の方は男性でエタノールで20~30ml(日本酒なら1合、ビール中瓶1本)で女性はその半分にし休肝日を設けることが良いようです

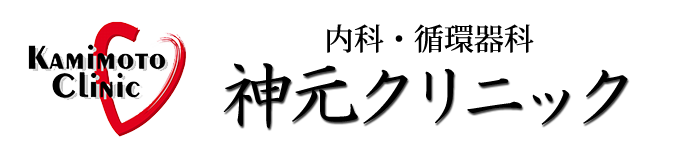
〒599-8233
大阪府堺市中区大野芝町180 神工ビル2F
Tel.072-235-7711
Fax. 072-235-4611
※セールス・勧誘・人材派遣などのFAXは、ご遠慮願います。
・内科・循環器内科
