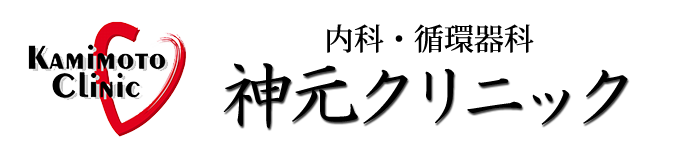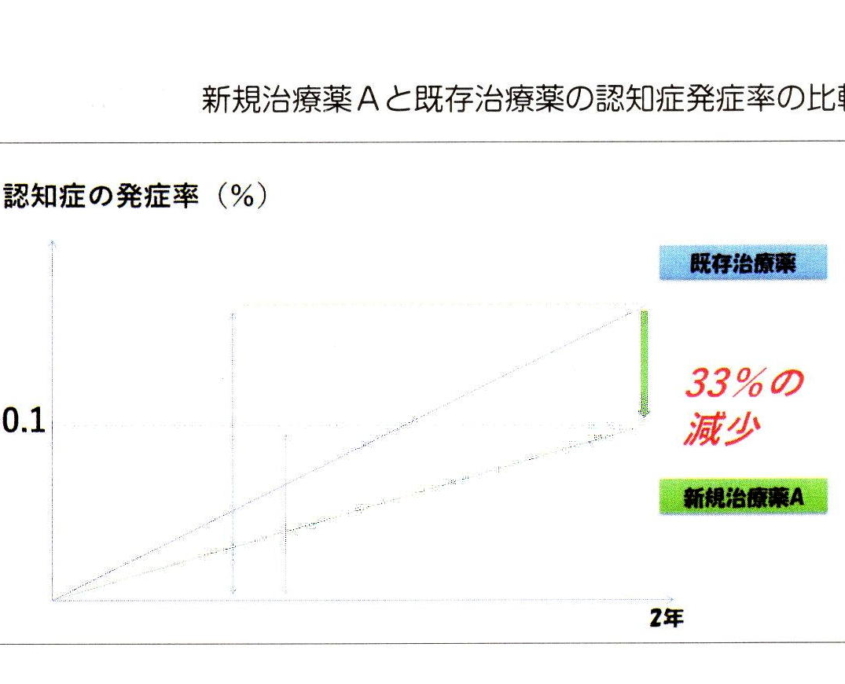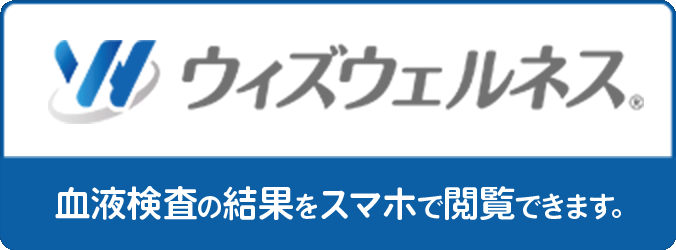10年以上前の話ですが、私が実際に経験したことを紹介したいと思います。
HIV(エイズのウィルス)のスクリーニング検査は感度99.9%、特異度99.9%の優れた検査です。
ある日20歳過ぎの若い女性が健診(たしか献血だったと思います)でHIV陽性を指摘されたと受診されました。
その方は、自分はそんなウィルスに感染するようなことは全く身に覚えがないとのことでした。
そのことを言うと家族から「嘘つき」と言われたと、目に涙を浮かべながら話されました。
はたして、この女性は本当に噓をついているのでしょうか?
ところで感度と特異度とは何でしょうか?
感度は「感染者を陽性と判定する確率」で
特異度は「非感染者を陰性と判定する確率」です。
日本におけるHIV陽性者は約10万人にひとりです。
例えば、日本人10万人にHIVのスクリーニング検査をした場合、その10万人にはHIV感染者が1名と非感染者が99,999人含まれます。
その感染者1人は99.9%の確率で陽性ですから0.999人即ちほぼ1人の陽性者がいることになります。
特異度99.9%とは100人の非感染者を99.9%の確率で陰性と判断しますから、言い換えると100人のうち0.1人の偽陽性者がいることになります。
ですので、99,999人のうち0.1%つまり99.9人=約100人の偽陽性者がいることになります。
まとめますと、日本人10万人にHIVスクリーニング検査をすると1名の感染者と100名の非感染者が陽性と判定され、
スクリーニング検査でHIV陽性と判断された場合100/101の確率で偽陽性です。
その女性は2次精密検査でHIVに感染していないことが証明されました。
これは正しい知識を持たず、先入観だけで物事を判断したために重大な人権侵害を犯した例です。
似たようなことはコロナウィルスパンデミックでもありました。