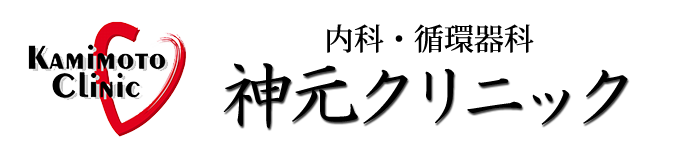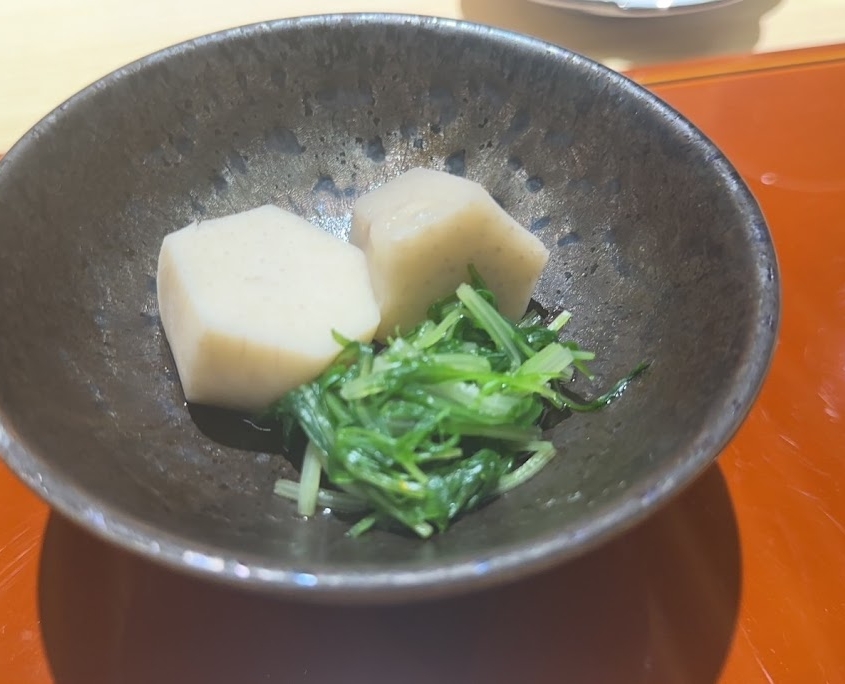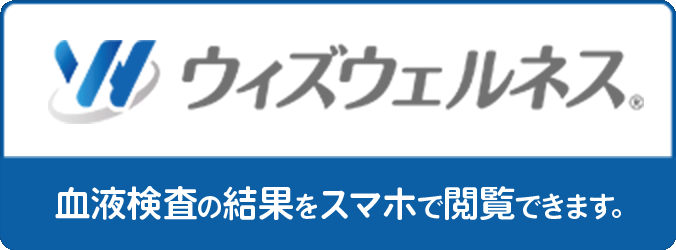現在心不全治療薬の柱と言われる薬剤は
・ベータ遮断薬
・アンジオテンシン変換酵素阻害薬/アルドステロン受容体拮抗薬
・SGLT2
・ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
の4種類で俗にFantastic Fourと呼ばれたりします。
このうちSGLT2は糖尿病治療薬として開発されたものの、発売後に糖尿病のある無しに関わらず心不全の予後を改善することが判明し心不全治療薬として認可されました。
これは大規模臨床研究という、患者さんを長期間追跡調査した結果に基づいて導かれた結果です。
大規模臨床研究は常に多くのものが進行中で、次々に新しい結果が学会に発表されます。
これらのデータの蓄積からガイドラインも定期的に見直されます。
最近の臨床研究「STEP-HFpEF」によると、やはり糖尿病治療薬のセマグルチドが糖尿病がある無しに関わらず肥満患者の心不全の症状を改善したそうです。
このセマグルチドは巷では痩せ薬としても話題になっている薬です。
長期の予後改善データではありませんが、今後のデータによってはFantastic Fiveということになるかもしれませんね。
私が循環器領域の臨床研究結果をチェックするのに用いているサイトの一つは
https://www.ebm-library.jp/circ/trial/index_top.html
です。
とても分かりやすく解説されていますので興味のある方はご覧ください。