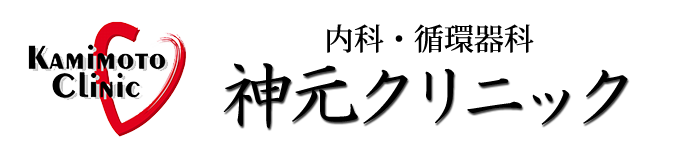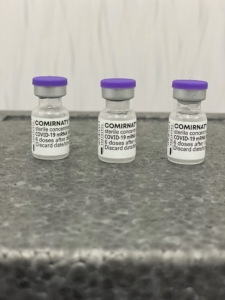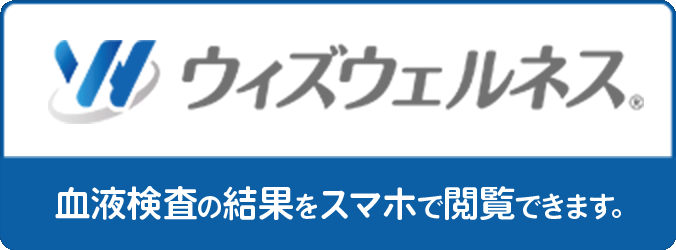コロナウィルスパンデミックで本当に多くのことを経験し多くのことを学びました。
現在当院で実施している発熱外来は、発熱または上気道炎症状のある方は受診前に予め問診をし階下の別室で診察をする、発熱患者さんを一般の患者さんから完全に隔離するという方法です。
これはもちろん新型コロナ感染症を念頭に置いたものなのですが、どうして今までこのような方式をとらなかったのだろうと自問自答することがあります。
パンデミック前を思い出せば、特に冬の風邪の季節にはどこの医療機関も同じ待合室に糖尿病の方、喘息でステロイドホルモンを服用されている方、膠原病で免疫抑制剤を使用中の方や肺気腫の方が風邪やインフルエンザの方と一緒にお待ちでした。
新型コロナ肺炎を診療するようになって感染対策に配慮するようになった今から考えると、以前はなんと配慮のないことをしていたのかと痛感します。
単なる風邪でも肺気腫の方や免疫機能の抑制されている方は時として致死的になります。
いつかこの新型コロナウィルスパンデミックが終息しても、私は現在の発熱外来という診療方法を継続しようと思います。