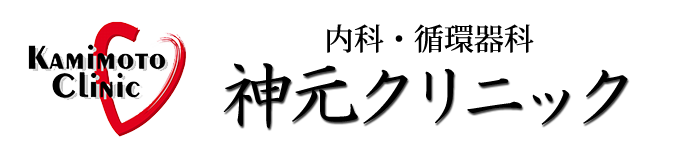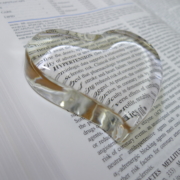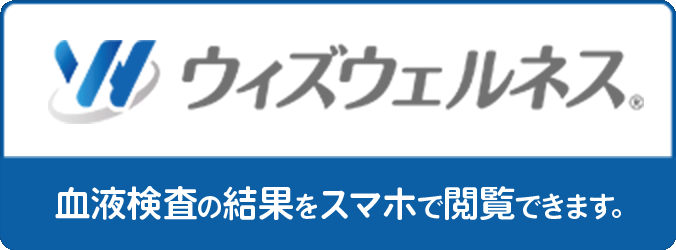高血圧の話 69 高血圧と慢性腎臓病
慢性腎臓病とは
・糸球体濾過率60以下
・持続する蛋白尿
のいずれかに該当する場合を指します
実は慢性腎臓病という病名は比較的新しく私が研修医の頃はこういう呼び方はしませんでした
腎硬化症、IgA腎症、膜性腎症、巣状糸球体硬化症、膜性増殖性糸球体腎炎や糖尿病性腎症などと主に糸球体の病理診断を元に診断され目標は透析回避でした
しかしその後、こういった糸球体疾患の方々の命を脅かすのは末期腎不全よりむしろ脳卒中や心臓疾患などの方がずっと多いということが統計的に証明され、治療目標は透析回避よりむしろ心血管疾患予防にシフトしました
腎機能低下は一旦始まると自動的にどんどん低下するという性質があります
BrennerのHyper filtration theory (糸球体過剰ろ過仮説)はこの性質をうまく説明しています
腎臓で血液をろ過し尿を作る糸球体は片方の腎臓で約100万個ありますが、腎機能低下とはこの100万個全ての糸球体の機能が少しずつ低下するのではなく機能を失った糸球体がところどころに出現し正常な糸球体の数が減少する状態です
残された糸球体一つ一つには過負荷がかかり、ろ過を多くするために糸球体の出口の動脈を収縮させてろ過する圧を上昇させ全体としてなんとか機能を保ちます
つまり残された正常な糸球体にかなりの負担をかけている状態です
この状況ではさらにいくつかの糸球体が過負荷により機能を失い、正常な糸球体がさらに減っていくという説です
ですので腎機能は低下すればその低下自体がさらなる低下の原因になります
このため糸球体の濾過圧を低下させる降圧剤、主にアンジオテンシン受容体拮抗薬が治療薬として用いられます
本年改定された新しい高血圧治療ガイドラインでは降圧目標が一律に130/80(家庭血圧125/75)未満とされていますが、その目標を達するために選択するべき薬剤はやはりアンジオテンシン受容体拮抗薬です
ただし慢性腎臓病のうちでも有効性が証明されているのは蛋白尿が陽性のもののみです
これは糸球体硬化以外の腎硬化症などが存在し、そういった場合にはむしろ逆効果になる場合があるからです
糖尿病性腎症にはアンジオテンシン受容体拮抗薬が最適とされていますがこれもやはり蛋白尿がある、すなはち糸球体疾患である場合のみです
降圧剤は適応を誤ると、一見血圧は低下していても臓器保護という観点では逆効果になる場合があります